2021年01月13日
健康長寿日本一 長野県 男性の平均寿命が80.88歳で1990年以降5回連続の1位、女性が87.18歳で初めての1位
健康長寿 長野県

長野県は、日本の屋根のような寒冷地でありながら、健康県ではないかと気づいたのは、1986年頃である。その頃は、そのころは、寒冷地は寿命が短いと言うのが定説であった。ところが1985年の長野県の平均寿命をみると、男4位、女7位であった。吉村県知事も非常に興味を示されて、県衛生部に調査させた。当時の調査の結果は、「長野県は海に面していないのでタンパク源がなく、そのためにいろいろのものを食べた。それがいい結果を生んでいるが、これからはだんだんと寿命も短くなる一時的現象だ。」と言うものだった。ところがそれから十年、長野の平均寿命はどんどんのびて、ついに男性は日本1位に、女性は4位になった。それだけではなく、長野県の老人医療費は、一人平均で北海道の半分、全国平均より約20万円も安いことがわかった。全国の各県の老人医療費が長野県並になれば、2兆円以上の節約になることもわかった。
こう言った点に注目した国保中央会は、1996年度の研究として、「市町村における医療費の背景要因に関する報告書」をまとめた。この調査の過程で長野県は健康県ではあるが、その割に100才老人は少なく、つまり長く生きるが、死ぬまで元気で、死ぬ年齢はそれほど長くないと言うことも分かった。これをppk(ピン・ピン・コロり)といって、一種、理想とも言える状態で、おおくの国民も知りたがっている。この調査では、長野県の老人医療費の安い理由は、他県に比べて医師が少ない、空きベットがあっても病院が在宅介護をすすめる、第二の人生として長野県民の多くが農作業をしていて生き甲斐がある、などのことが分かった。長野県全体の健康状態は世界に誇れるものだとおもうし、日本全体が長野から学ぶところも多いと思う。しかし、まずこの誇るべき事実を長野県の方々に理解し、納得してもらいたい。本当は、長野の実態をどう行政に生かすかという重要な問題があり。これが厚生省の仕事である。ただ医療費のリストラを叫ぶだけではなく、どの県も長野県のようにすれば老人医療費だけではなく、若い人の医療費を含めれば三兆円ぐらいの節約になるのではないか。この本を読んで考えて欲しい。「ppkのすすめ」医事評論家 水野肇 共著 紀伊国屋書店 出版
田園ルネッサンス
Iターンは1500人超す
豊かさ・満足度、長野県が全国1位
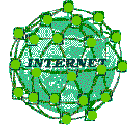
インターネットで村おこし、町おこし。
ネットワークで信州を豊かにする
the United People of the World
2021年01月13日
信州の暮らし インターネット安曇野
信州の暮らし
信州の冬の寒さを心配している人が多いかと思います。長野県は全県にわたって空気が澄み、日照時間が長いために、冬の寒さも太陽のおかげであまり気にならずに暮らせます。太陽のありがたさを体で感じます。春が待ちどうしくもありますが、信州の冬は決して陰鬱な季節ではありません。
長寿県である理由は、信州人の風土・気候に向き合って暮らす習慣にあります。健康を増進できる生活環境が自然の中にあることこそが、長野県に生活する意味だと思います。あらためて土とは?水とは?空気とは?私たちが生きてゆくために必要なものが身近にある安堵感が、故郷に愛着がもてる由縁です。山村には文明人の癒しの場がいたるところに眠っています。
また、親の教育観により子どもの住む場所が決まってしまいます。啓蒙期に必要な教育を考えてみると、信州は子どもたちにとって豊かな宝庫です。人間は、もともと管理されるために生まれて来たのではありません。今、学級崩壊が社会問題になっていますが、この理由は、子どもたちを取り巻く大人たちに目に見えないものを感じ取る力が無くなってしまったからだと思います。空は鳥を自由に飛ばせ、海は魚をほしいままに泳がせる。大人はこの空や海の大らかさを忘れて鳥や魚になってしまい、理に走り、情がなくなってしまいました。
また、傷ついた心を癒してくれる祈りの場が、身近かになくなってしまいました。このために自分の身を痛めつけたり、より刺激を求めて放縦してしまいます。これが社会現象となっています。世の中から聖職者が居なくなってしまったからです。
信州に移り住むことですべてが解決するとは思いませんが、子どもたちの生命力を生かすことは事実だと思います。
田園ルネッサンス
健康長寿 信州
Iターンは1500人超す
豊かさ・満足度、長野県が全国1位
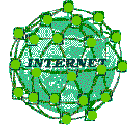
インターネットで村おこし、町おこし。
ネットワークで信州を豊かにする
the United People of the World
2021年01月13日
信州へ帰ろう!Iターン就職者 I ・Uターン Jターン 長野県
Iターンは1500人超す(89’4月~)(信毎1998)
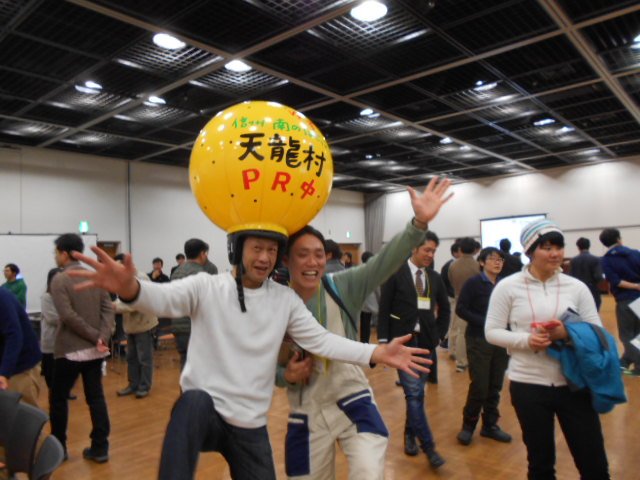
他県から県内に移って就職するIターン就職者数が、89年4月から今年7月末までの累計で1512人に達したことが10日、長野県雇用対策室のまとめで分かった。「長野県はIターン先としては全国的にも人気が高い方で、一定のPR効果も出ている」と分析している。同対策室によると、Iターンは91年度の209人がピークで、昨年度も193人の就職が決まった。今年度(4~7月)は48人で、景気低迷の中にあっても前年同期より1人減にとどまっている。
産業別では、製造業が637人で42.1%を占め、次いで▽サービス業387人建設業215人▽卸・小売業196人の順出身都道府県別では、県外出身者が757人で50.1%に達し、東京都(207人、神奈川県(86人)、大阪府(70人)が多い。(信毎1998.08.12)
大北地方(大町市、白馬村、小谷村)へのI ・Uターン 6年余で500人超す。
大北地方へのI ・Uターン者が、統計をとり始めた92年5月から6年関余で500人を超えたことが24日、大町公共職安安定所のまとめで明らかになった。97年度には、1年間で119人が就職しており、同職安と大北地域雇用開発協議会は、同地方の恵まれた自然環境に加え、求人誌への掲載など自治体の積極的な取組が功を奏したと分析している。
同職安によると、8月末までのI ・Uターン者は509人。500人目までの内訳は、年齢別で30歳以下が206人で4割を占める。40歳以下まで含めると371人で、4分3は、比較的若い世代であることが特長だ。
県外出身者は、456人で、首都圏や名古屋、関西が大半を占めている。
就職後のアンケートによると、I ・Uターンのキッカケは、登山やスキーなどで訪れた際、自然環境にあこがれて移り住んだと言う回答が目立つ。さらに、交友関係など、それまで生活していた都市部との接点を保ちたいと言う希望も強く、近年の交通網整備もI ・Uターン者増加につながったのではないかと同職安では分析している。(信毎1998.09.25)
Iターンは1500人超す
田園ルネッサンス
健康長寿 信州
豊かさ・満足度、長野県が全国1位
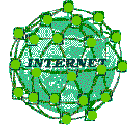
インターネットで村おこし、町おこし。
ネットワークで信州を豊かにする
the United People of the World
2021年01月13日
「豊かさ、満足度」長野県が1位 元気につながるふるさと信州 しあわせ信州
「豊かさ、満足度」長野県が1位
「生活の豊かさと満足度分析」三菱総合研究所

三菱総合研究所が20日発表した1998年版「生活の豊かさと満足度分析」によると、総合指標で長野県がトップ、宮城県、岡山県と続き、最下位は高知県だった。男女別で比べると、女性にとって1番豊かなのは長野県だが、男性は宮城県が1位。世代別では、10~20代は岡山県、30~40代は長野県、50~60代では滋賀県と「豊かさ1位」が分かれ地域によって異なる生活、社会条件が、多様な暮らしやすさとして受け止められていることがうかがえる。
調査は、住まい、交通、仕事、所得、消費、健康、家族、教育、生活環境など10項目について、600以上の統計をチェック。全国で約1500人の住民アンケートも加えて、住民の満足度を反映させた「豊かさ指標」として男女、世代別に算出した。
それによると、家賃、リサイクル率などを参考にした「住まい」の豊かさでは、男女別に加え10~20代、30~40代、50~60代の3世代ともすべて長野県が1位だった。
長野県は貯蓄・資産でも全国1位。失業率や労働時間を基にした「仕事」では、長崎県、大分県に次いで3位を占めた。
豊かさを測る指標としては、経済企画庁が各種統計を生活分野別に組み合わせ「豊かさ指標」として毎年発表している。三菱総研による民間版豊かさ指標は、住民アンケートを組み合わせ、地域での「満足度」を加味した点が特徴だ。(1998.10.21 信濃毎日新聞)
田園ルネッサンス
健康長寿 信州
Iターンは1500人超す
豊かさ・満足度、長野県が全国1位
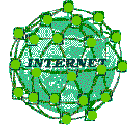
インターネットで村おこし、町おこし。
ネットワークで信州を豊かにする
the United People of the World
2021年01月13日
田園ルネッサンス 定年帰農ブーム 逆都市化現象!故郷に帰ろう!
田園ルネッサンス
太陽の下で農作業の真似事をしていると大粒の汗がしたたり落ちる。舐めてみるとしょっぱい。生きているな!生かされているな!と宇宙を司る神の存在が実感できる瞬間です。何を持っても代えがたく、この爽快感はたまらなく有り難い。生命の保障をしてくれているようで。親父が稲を眺めながら一服している姿が愛おしく懐かしい。
帰りなんいざ 田園まさにあれなんとす
こんな歌い出しで始まる「帰去来の辞」は1500年以上前の中国の詩人、陶淵明の隠とん生活宣言の詩だ。今こそ、自然に帰り、母なる懐に抱かれ、その鼓動を体で感じ、心を大いに遊す。 この大いなる自然の有情により、失いかけている生命力、精神力を回復させ、かけがえのない自然と共に生きる。この詩にあやかったわけでもないだろうが、最近、定年後、田園に帰り、農耕にいそしむ人々が急増中。その動きを特集した雑誌が次々にベストセラーとなっている。
年々減る日本の農業人口の中で、60歳以上の新規就農者は1994年4万5千人だったのが、96年には5万9千人と急増。そんな人々を特集した雑誌「現代農業」(農文協刊)の増刊号「定年帰農ー6万人の人生二毛作」が今年1月に刊行されると、このことが新聞やテレビ番組などでしばしば取り上げられ、「定年帰農」は時代の流行語のひとつとなった。増刊号は増刷され、7万部も売れた。
農文協では続く増刊号として7月に「田園住宅」を、10月には「田園就職」を刊行。「田園住宅」では定年帰農の拠点となる家づくりや古民家再生法、長期宿泊施設付き貸し農園などの事例などを取り上げ、「田園就職」では農業法人への就職や国産大豆を使った豆腐づくりのミニプラントなど自営農業に限らない農村の仕事の面白さも紹介している。これらも各6万部だ。
反響は国内にとどまらず、最近では日本人の生活変化に注目した米国のワシントン・ポスト紙が農文協を取材するなど、定年帰農ブームは海外にまで注目されだした。
このブームに触発され過去を調べると、46年6月に「帰農時代」という本が刊行されていることも分かった。著者は柴田義勝さん。東京や名古屋で10数年都市生活をしたあと帰農した元新聞記者だ。
→ 孤独は山になく、街にある
それは敗戦から間もない時代。今、経済戦争に負けて第二の敗戦が言われる中での「定年帰農」である。時代の大きな変化に直面した時、日本人にとって「帰農」や「田園」は心動かされる生活スタイルであり、暮らしの場であるようだ。
農文協の甲斐良治さんも「イギリスやフランスでは1950年から農村人口の伸びが都市を上回る『逆都市化現象』が始まり、『田園ルネサンス』『田園革命』などと言われています。日本もそんな歴史の転換点に立っ他のではないでしょうか」と言う。(信濃毎日新聞 1998.12.25)
種を蒔けば芽が出、実を結ぶ。この因果関係が、わたしたちの生活に見い出せなくなってきています。これがわたしたちを不安にしています。人の気紛れを基調にした社会経済から、一歩下がり、こころのよりどころを大自然の大順にもとめようとする人が現われても不思議ではありません。
私たちのふるさと信州は県をあげて、ふるさと定住事業に取り組んでいます。嫁さんや婿さんも、また、退職されてのんびりと暮らしたいご夫婦も大歓迎です。そして、働き盛りの人も、都会をマーケットに田舎暮らしをすることが、交通網や通信インフラの発達のおかげで可能になっています。インターネット安曇野では、「いざ、故郷へ帰ろう!都会と信州とを生活の舞台とするライフスタイルはいかがでしょうか。」Iターン、Uターンキャンペーンを行っています。
信州には人類理想の生き方がある
健康長寿 信州
Iターンは1500人超す
豊かさ・満足度、長野県が全国1位
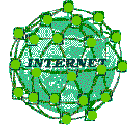
インターネットで村おこし、町おこし。
ネットワークで信州を豊かにする
the United People of the World
2021年01月13日
人間性の回復、自然への回帰!田舎暮らしのススメ!故郷へ帰ろう
人間性の回復 地域共同体
孤独は山になく、街にある 無縁社会
 >
>
私は、住み慣れた安曇野から一年間ほど渋谷区代々木のオフィースマンションに移って仕事をしたことがあります。(1997~98)
都会で生活をしてみて改めて思い知らされたことは、生活することすべてにお金がかかり、お金の感覚を麻痺させないと暮せなく、お金を持っていない人には、非情な街だと言うことです。これでは普通の商売では挫折感を味わうだけだと思ったり、高層ビルを見上げ、あそこで働いている人々は、一体何をやって飯を食っているのか、あれだけのものを賄えるそんな良い仕事が果たしてあるのかと不思議に思ったほどです。
交通渋滞や喧騒と無機質な生活空間、溢れる情報そして疎外感、街には溢れる残飯、他人ごととは思えないホームレスの出現、髪を焦がし、肌を焼き、皮膚に金具をさし自虐する若者たち、企業倒産や一家離散に引導を渡す高利貸し(商工ローン、サラ金)のCM放映、相続税のために立派な屋敷が無残にもぎ取られ、そこに現われた痛々しい光景、そして、何よりも無秩序に肥大化した東京、そこに封じ込められ、精神的に圧力をかけられ、じっとしてはいられない人々。人々はこの辛い現実から目をそらし、この苛立ちに空しさを知り、疑うことをやめ、馴致してしまい、諦めることで生活をエンジョイしているように思え、何かが違うと違和感を持ったものです。この不安は、単に首都機能の移転や景気が良くなれば解決する問題とは到底思えません。
私は、よく仕事の帰りに明治神宮に参拝したり、参道に大きく掲げられている五箇条の御誓文を心で唱えることで、生きていることの証を感じたものです。鬱蒼と繁る大木の中を歩きながら思ったことは、信州には、これだけ立派な大木は育ちません。首都東京は、ものを育む豊穰な土地の上に建てられています。だから日本の首都になったのではないかと思うようになりました。今、問題にしなければならないことは、首都機能を移すことではなく、私たちの心の在り方を問い直してみることだと思うのです。この大変な時にもう一度、明治維新を導いた大我を学び、勇気をもって現実を見つめることだと思います。
モノをバラバラに破壊し、分析・解析する学問は、時代と共に大きく発達しました。しかし、バラバラにしたモノを統合・再構築させる気高い思想や、それをもう一度元に戻す科学技術は今だに持ち得ていません。再生不能なモノが、不安定な状態で、溜まりに溜まり秩序の保てない社会になってしまいました。これは、科学技術の限界を如実に現わしています。このままでは、盲目に努力し、破滅の道を歩んでいるように思えてなりません。
しかし、一方で、私たちは、欲望にまかせ、どんどんモノをつくり、使い捨てる消費社会から、浪費を抑え、生活水準を下げてでも、今あるモノを節約し、修理し、大切に使い、そしてリサイクルする循環型の社会に戻ろうとする気運が芽生えています。「もったいない」と言う素朴な気持ちが生活に戻ってきました。3年で買え換えていたクルマを、10年間乗り続けようという、モノに対する大きな心の変化ですから、今までの不況とは異なり、既存の設備型産業は、適正規模になるまで、設備の廃棄をしたり、再構築し直したり、産業そのものを循環型にダウンサイジングせざるを得なくなっています。産業構造の大変革です。
これは、国や企業や家庭でも収入に見合った経営に戻すことを意味しています。これまでのマネーゲームでのツケを経営利潤で埋めようとしている分けです。苦しくて当然です。この中にあって3万人もの自殺者を出しています。この歴史の流れに責任をとれる人はいません。過去の精算はするとしても、命までも絶つ必要はありません。新しい時代にもがき、新しい時代をつくるんだと言う気概で、時代、地球が求めている産業を起こすことに積中すべきです。モノやエネルギーを際限なく消費しつづける時代は終わりました。経済の永続的な発展は、あり得ない現実に直面しています。
また、全て国家予算内での社会福祉も行き詰まりをみせ、お金に頼る福祉行政から地域住民が、自由意志で時間と労働を、地域社会に供出する民間ボランテイアの力に委ねざるを得なくなっています。社会コストの削減と制度の簡素化を考えなければなりません。この原点は、農村社会にあります。人間らしい暮しを願うものであれば、自ずと都会の鬱積したエネルギーは、都会から地方に大きく流れ、等身大のシンプルライフに落ち着いて行くはずです。
想像してみてください!何もかも飲み込んで行くブラックホールのように、今、コンピューターが現存するモノや制度をどんどん飲み込んでいます。将にもう一つの現実が、コンピューターに集積され、現実と相待する裏の世界が形成されています。この裏の世界が、時間も空間も超越したことにより、私たちの意志決定と行動の在り方で大きく社会を変えることができます。そして、これからのエネルギー資源や地球環境を考えると万民が、太陽の恩恵に感謝し、太陽から食糧やエネルギーを授かり、その中で生きるシンプルライフを是とする宇宙観とそれを分かち合い助け合う暮らしが求められています。これは、日本の暮しの歴史を探って見ると、自然と共生する文化こそが、日本の生活様式であったことに気づくはずです。
土地のないマンションが7、000万円もしています。田舎では太陽光発電、下水道、菜園つきの自給自足型の一軒家が新築でき、その上、老後の生活費がこれで賄えます。自然や他人から隔離された閉鎖型の住まいよりも、日本の四時を楽しみ、地縁、血縁の悲喜こもごもに人間らしさを享受し、人にも、自然にもオープンに大らかに生き、そして野辺の送りで地に還る。このあたりまえの生き方がいい。
太陽の下、元気なお年寄りたちが、童心に戻ってゲートボールに興じています。信州には、おだやかでのどかな暮らしがあります。今の言葉で言うと社会福祉ですが、時間や労働の貸し借りが、地域社会の暮らしの中に綿連と生きています。お互いさまと、いたわり合う民情が、人々の間に今も生きています。この心の貸借表の帳尻が、時間が経ってみると、ピタリと合うからこそ、今も、世代を超えて受け継がれています。この心の結びつきを結(ゆ)いといいます。このおもいやりや分かち合う気持ちを持てる人は、自然の恩恵とともに、信州の人々が温かく迎えてくれます。自然や社会は、個人にとってみればもともと非情なものです。これに抗する生き方が、肩を寄せ合い、半分っこし、分かち合い、地縁血縁を強めてきました。このことを都会人よ笑わないでほしい。お金にたよる社会保障が、破綻し、お金をかけないでも安心して暮せる方法が、今、必要です。私たち日本人の精神的風土は、自然を崇め、土着の家族や地域社会にあったはずです。これが「もののあわれ」を血とする私たち日本人の行動様式です。
今、結婚を敢えてしない若者が増えてします。それ故に結婚ができないでいる若者が悩んでいます。人の気持ちですから性急な解決策はありませんが、人にも、自然にもオープンに生き、有情を知ることにあると思います。母親の選んだところが、生まれてくる子どもたちのふるさと。すべてのものが友達だったふるさと。このふるさとを大人の郷愁にしてしまわないで、うまれくる子供たちのために何を優先させるべきかを考える時です。本当は、人が生まれるのは、大自然が人を生ましめているのであって、各人はそれを自分の子と思っていますが、正しくは、大自然の子です。それを育てるも大自然であって、親はそれに手を貸すだけです。
人間は「自然」に遊び戯れ喜ぶ本能があります。私たちは、自然から遠ざかるにつれ、菌に対する抵抗力がなくなり、免疫不全の体になるんではないかと言う不安があります。特に「土」がきたない物だと言う考えが衛生教育に取り入れられてから顕著です。ソフトドリンクやビールを、水代わりに飲まなければならない生活環境は、やはり異常です。
しかし、本能的に、人間が自然に戻りだしています。耳が痛いほどの静けさ、手の届きそうな満天の星、ガブガブ飲める水 大切にしたいモノばかりです。
私たちのふるさと信州は県をあげて、ふるさと定住事業に取り組んでいます。嫁さんや婿さんも、また、退職されてのんびりと暮らしたいご夫婦も大歓迎です。そして、働き盛りの人も、都会をマーケットに田舎暮らしをすることが、交通網や通信インフラの発達のおかげで可能になっています。インターネット安曇野では、「いざ、故郷へ帰ろう」を旗印にIターン、Uターンキャンペーンを行っています。
・田園ルネッサンス
・都会と信州とを生活の舞台とするライフスタイルはいかがでしょうか。
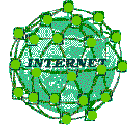
インターネットで村おこし、町おこし。
ネットワークで信州を豊かにする
the United People of the World




